秋の農作業の一段落し、今日は近所の友人たちと多度津沖でイイダコ釣りをしました。
波の穏やか、天候も最高で、たくさんのイイダコが釣れました。
船は職場の元上司所有のF丸です。
5人で、クーラーボックス2杯も釣れ、近所へのおそそわけをし、生でしっかりと刺身で頂いても、かなりの量があり、スミ抜きし、足を塩もみし、とりあえずゆでました。
明日からは、たこ焼きに、おでんに、タコを食べるのがとっても楽しみです。
農産物をはぐくむ「水」、「土」、「光」の恵みを生かした農産物生産を行っています。
仕事で、真庭市落合公民館に行ったところ、梅の花の展示会をしていました。 市内自慢の梅の盆栽を持ち寄って開催されるイベントで、出展数200を超す赤や白の見事な梅が立ち並んでいました。
平成16年の町村合併で旧落合町は真庭市となりましたが、旧落合町の町の花は「白梅」、町の木は「ウメ」、そして町の鳥は「ウグイス」です。
各家庭にも、梅の木が植えられており。今日は自慢の盆栽が並んでいました。バックでは、ウグイスの鳴き声も流れていました。

| ウメ種類は私にはよくわかりませんが、白梅、紅梅、しだれ梅などたくさん並んでいました。 |
ごあいさつ
厳しい冬の寒さの中で、春を呼び招くがごとく一輪また一輪と咲き殆める梅の花。その花の清純さ、華やかさ、香りのよさは古くから親しまれており、古の時代から梅花を題材に多くの歌が詠まれています。
落合地区では、菅原道真公ゆかりの箸立天満宮(落合垂水地内)にある梅にちなんで、梅の里づくりを進めてきました。地域の多くの方々が、丹精こめて一年間管理をし、この梅花展にむけて育ててきた梅の盆栽。春を告げるイベントとして、14回目を迎える今年の梅は、昨年末からの異常寒波に耐えて見事に咲き誇っています。落合を愛し梅の花を愛する住民皆さんの、自慢の梅盆栽をゆっくりご鑑賞ください。
第14回おちあい梅花展実行委員会
JR境港駅です。鬼太郎列車こと妖怪列車が駅のホームに止まっていました 水木ロードを散策してみました。私にはなぜか、「田の神」と「泥田坊」が心に残りました。たくさんの妖怪がいましたが、なぜか農業に因んだ妖怪が多いと思います。これは日本は昔、ほとんどの庶民が農民であったせいだとは思いますが、昨今の農業の担い手不足や耕作放棄地の発生など農業や田んぼに若者の目が向けられなくなった時代に、何かもの悲しく見えました。
水木ロードを散策してみました。私にはなぜか、「田の神」と「泥田坊」が心に残りました。たくさんの妖怪がいましたが、なぜか農業に因んだ妖怪が多いと思います。これは日本は昔、ほとんどの庶民が農民であったせいだとは思いますが、昨今の農業の担い手不足や耕作放棄地の発生など農業や田んぼに若者の目が向けられなくなった時代に、何かもの悲しく見えました。
私たちの村では、旧暦の10月に亥(い)の日が2回あれば1回目の3回あれば2回目の亥の日に祭ります。
この日は大根が音をたてて太るから大根畑に入ることが禁じられて農作業は休みます。
亥の子は百姓の神(田の神)でアカギレの神様だともいわれています。
モチをつき、ユズとともに神に供えます。また、この日に「コタツ」を開けると火事にならないそうです。
夕刻に子供たちが「亥の子、亥の子、亥の子晩に、祝わんうちは、鬼うめ、じゃうめ、角の生えた子うめ」と大声を出して近所を廻ったそうです。

泥田坊の話を職場の同僚から聞いて思わず感動しました。
泥田坊は昔、田を子孫のために一生懸命に耕していた男の息子が、農業せず田を他人に田を売ってしまい、夜になると「田を返せ」と言って出てくるそうです。
最近は、農業の情勢も厳しく、田んぼを耕す後継者がどんどん減っています。加えて、普通の米作りのではなかなか収益性が上がらず、耕作放棄されていく田んぼが増えています。
いま中国地方のあちこちで耕作放棄地が目立つようになりました。他人に売らずとも、先祖伝来の田が荒らされていくのには悲しい思いがあります。とは言っても米作りでは儲からないし、難しい時節になりました。いまあちこちの耕作放棄でむかし「田を返せ」と嘆いていた泥田坊は今日では「荒れた田んぼを元に戻してくれ」と悲壮な叫び声を上げているような気がします。
 |
 |
| 静かな流れの堀川。両岸には、いろんな花なんかが植えられていました。ちょうど「ツワブキ」がきれいな黄色の花を咲かせていました。 | カルガモ君の登場 |
 |
 |
| 船の中は意外に天井が低い。 前方に低い橋が近づいてきました。 |
なんと、低い橋が近づくと天井がぐっと下がってきました。 みんな頭だけでなく体も低くして・・・ |
 |
| 松江城が近づいてきました。堀川は松江城の築城時につくられたそうです。 |
 |
 |
| 松江城の天守閣は四方が見渡せる天守閣で、このタイプのものは現存するものでは、松江城の他には姫路城、松本城くらいしかないそうです。 | こちらは武家屋敷。立派な松が植えられています。 この中に「八雲庵」という美味しいそば屋があり、先ほど昼食をとったばかりでしたが、べつ腹に、ソバとぜんざいを頂戴しました。美味でした。 |
 |
 |
| とてもユーモラスで、親切でしかも操船技術の高い船頭さんでした。今度はもっと暖かい時期に来ようと思いました。 | 楽しかった「こたつ船」でした。右下の松江地ビールを飲み過ぎて赤ら顔になってるのが筆者です。 |
 |
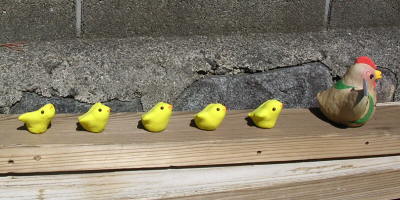 |
岡山県勝山町では、県北に春を告げるイベントとして、この時期「勝山のお雛まつり」が開催されます。勝山町の中心部の町並み保存地区では、約160軒の民家や商家で軒先や店先に様々なお雛様が飾られます。民家の中には庭先にさりげなく飾られているものもあったり、老人グループの作品、川柳とともに飾られているもの、皆さん趣向を凝らした楽しい雛祭りです。
勝山町は、江戸時代、三浦藩二万三千石の城下町でした。普段は、ひっそりとした静かな山間の町ですが、この雛祭りの期間中は町の人口の約3倍の3万人が訪れ、にぎやかになります。
 |
 |
| 普段は静かな町並みですが、今日は東京の原宿並みの賑わいでした。 | |
 |
 |
| かわいい | 老人クラブの力作 |
 |
 |
| 勝山は「のれんの」町でもあります |
 |
| 粋な川柳がたくさん |
 |
 |
| 岡山県北で多い「どろ天神」 | 「果物屋」さんの店先 |
 |
 |
| こちらは、「時計屋」さんですね | 地元の「農業協同組合」も参画しています |
 |
 |
| これはまた、竹の中のかわいい雛 | 勝山特産のブドウ「ピオーネ」も材料に |
 |
 |
| 勝山特産の高田硯(すずり)の石もひな人形に・・・・ | |