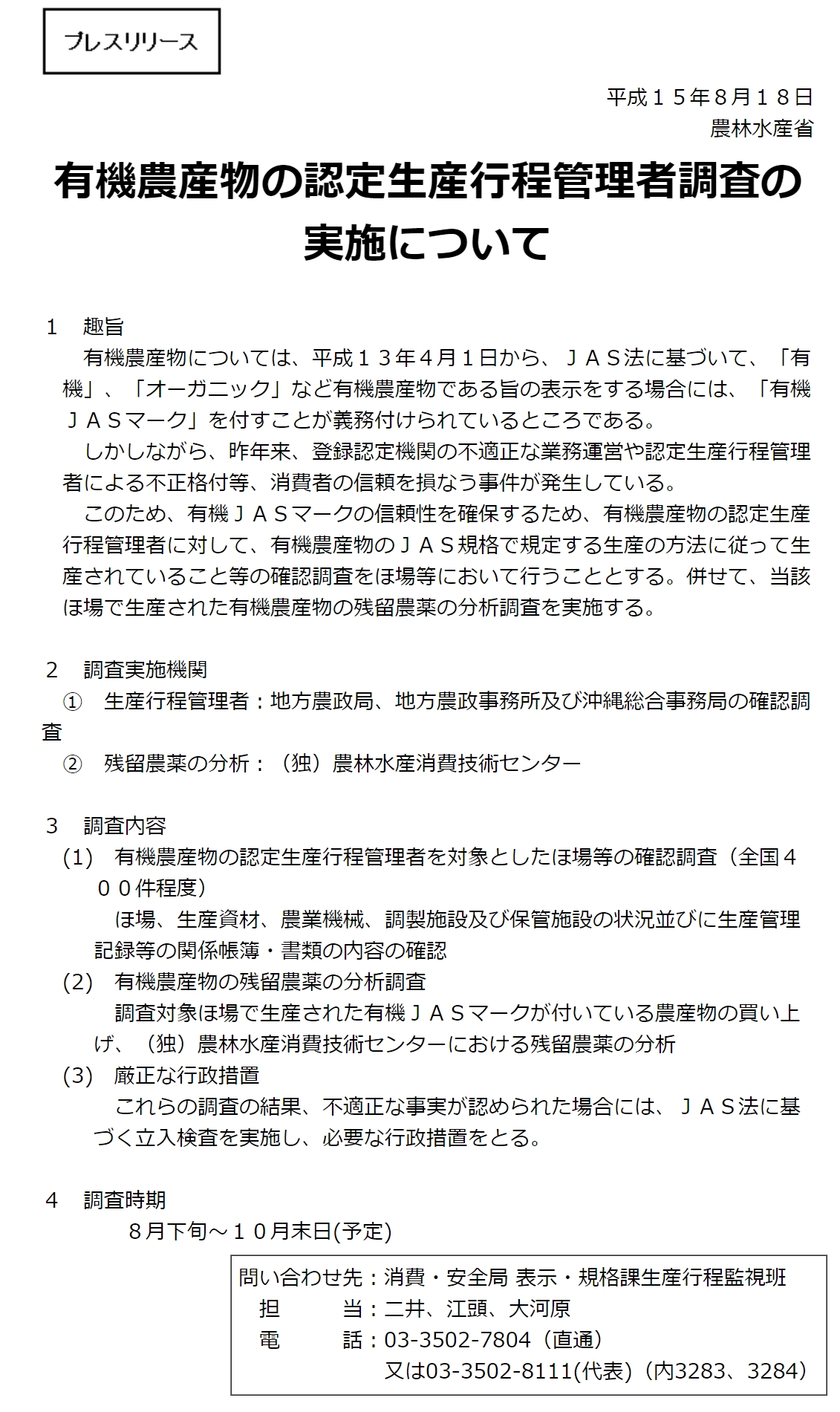タグ: organic
有機栽培ほ場に大豆の莢を散布しました
8月も終わり
アワノメイガ
有機栽培の稲に次なる難敵が
有機栽培の稲
ほ場巡回を行いました
本年も有機JASほ場の内部監査として、ほ場巡回を行い、生育状況等の確認と研修を行いました。
これは、有機JASに基づく籾村セーフティーライス倶楽部の「有機農産物の生産行程の管理及び格付の実施方法に関する業務規程」第19号にもとづき、籾村セーフティーライス倶楽部定める「生産管理方針」にそって栽培が行われていることを確認するとともに、ほ場での課題や今後の対策を会員相互で研鑽するために行うものです。
景山
(1号ほ場 有機栽培開始 平成7年)
昨年はコナギにやられてしまったほ場ですが、今年は稲の生育がコナギの生育に勝り、順調です。
(2号ほ場 有機栽培開始 平成9年)
こちらのほ場も、コナギ、イネミズゾウムシの被害が少なく、順調です。
治部
岸
(1号ほ場 5a 有機栽培開始 平成7年)
平成7年以来13年間有機JASで水稲栽培を行っていましたが、今年は大豆を栽培してみました。
(2号ほ場 有機栽培開始 平成9年)
昨年は大豆を栽培したほ場です。1年間畑状態で管理するとコナギの発生が減少するかと思いましたが、やっぱし今年もたくさんのコナギが発生しました。しかし、何とか稲が勝っているような感じです。
(3号ほ場 有機栽培開始 平成19年)
(4号ほ場 有機栽培開始 平成19年)
有機栽培2年目のほ場ですが、いきなりコナギの発生が多く、稲が痛めつけられています。
杉山
(1号ほ場 有機栽培開始 平成7年)
(2号ほ場 有機栽培開始 平成7年)
コナギは水生植物で、湛水状態で生育旺盛です。今年は田んぼを干し気味に管理し、何とか稲の方が生育が勝っているようです。

(3号ほ場 有機栽培開始 平成7年)
このほ場は特に干し気味の管理を行い、田植え後2週間目から田んぼを干して管理してきました。確かにコナギの生育に稲が勝っています。
コナギ以上に稲の生育を阻害するのが「イネミズゾウムシ」です。下の左の写真はイネミズゾウムシに加害された株です。根が非常に少なく、褐色になってしまった根が多いです。右の写真もイネミズゾウムシに加害され、蛹(土繭)も見えますが、イネミズゾウムシの食害以上に稲の発根があり、白い根も見えます。この株なら十分な収穫が期待できます。
播元(1号ほ場 有機栽培開始 平成14年)
昨年までは、除草機や手取り除草でコナギの生育を抑えていましたが、今年はコナギに押され気味です。
宮本
(1号ほ場 有機栽培開始 平成11年)
宮本会長のほ場です。こちらも毎年コナギには泣かされていますが、今年も、コナギ、イネミズゾウムシに押され気味です。これから再度、中耕除草を行い、稲の生育回復にチャレンジします。
光元
(1号ほ場 有機栽培開始 平成14年)
昨年は、黒大豆を栽培したほ場です。稲の生育は旺盛で順調ですが、今年はコナギは少ないのですが、「ヒエ」の発生がすこぶる多いようです。
また、生育が不良な株を抜いてみるとやっぱしイネミズゾウムシの土繭がしかり根についていました。
(2号ほ場 有機栽培開始 平成17年)
赤木
(1号ほ場 有機栽培開始 平成19年)
有機栽培水稲2年目で、生育は良好です。しかし、今年はしっかりとコナギが生え、まる三日かけて手取り除草し、今の生育に至っています。
今年は、4~6月は過去に例がないくらいの小雨でした。水溜や田植えの遅れ、田植え後の生育不良などもおきましたが、7月に入ったとたん毎日梅雨空が続きました。
今年も、会員のほ場を巡回して稲の出来具合を確認しました。
宮本 有機栽培7年目のほ場です。今年は、田植えkを工夫して動力除草機を縦横に押してみましたが、やはり、雑草の発生は多く、6月末から約2週間来る日も来る日も手取り除草に励みました。
大江
有機栽培4年目のほ場です。サツマイモ、ニンジンは順調に生育していますが、7月に入ってからの多雨の中、アスパラガスは今年は茎枯病に加え、雑草が繁茂して、生育不良です。
岸
有機栽培12年目のほ場です。今年は田植前に米糠100㎏、田植え後に菜種粕100㎏(いずれも10aあたり)散布し、田植え後3回動力除草機をかけ、約10日間にわたり、手取り除草しました。それでもコナギの発生は盛んで稲の生育は今一歩です。 今年は7月以降の長雨でやや稲が軟弱になり、全般的に葉を食害する害虫の発生が多い傾向にあります。イネアオムシやイナゴの幼虫が多く、葉っぱをかなり食害されました。
今年は7月以降の長雨でやや稲が軟弱になり、全般的に葉を食害する害虫の発生が多い傾向にあります。イネアオムシやイナゴの幼虫が多く、葉っぱをかなり食害されました。


播元
有機栽培4年目のほ場です生育は良好です.
景山
有機栽培12年目
今年もコナギとウキクサ
景山のこの田んぼは、天水田のため、田植え以降7月1日まで、1ヶ月にわたり、ほとんど田んぼに水が入りませんでした。このため、田んぼに大きなひび割れが出来てしまいました。一時は収穫を諦める程稲が痛みましたが、7月からの降雨でやっと稲が元気になりました。
写真のように、まだヒビが残っています。加えて、まだ地面も固く、写真のように長靴で田んぼに入っても少しも足が沈みません。分けつもまだまだ少なく、収量がやや心配です。
また、雑草は田植え後に水がなかったため、タカサブロウなどの湿性植物が中心に繁茂しています(右写真)。しかし、7月以降田に水が溜まった後は、タカサブロウの下から、コナギも生え始めました。田んぼか硬いため、動力除草機も使えず、また、手取りも困難であり、困っています。どうなることやら・・・・・・

杉山
この田んぼも有機栽培12年目です。杉山は毎年栽培方法に工夫を凝らし、今年は、基肥の有機653を通常の2~5倍量を投入し、除草機と手取りで、稲の生育を雑草の生育よりも勝ることに成功したようです。今のところ生育は順調です

倶楽部員の有機栽培ほ場の田植えも6月初めには終わり、全員の有機栽培ほ場を巡回してみました。
宮本隆治
有機栽培6年のほ場です。今年も宮本氏は菜種粕+動力除草機体系で除草対策を行っています。なぜは今年は浮き草が大発生しました。これでかえって他の雑草が抑えられて災い転じて福となるでしょうか??。

大江泰司
有機栽培3年目のほ場です。サツマイモはマルチ栽培できるのでよく雑草を抑えています。今年は、サツマイモにネキリ虫が多く発生しました。
ネキリ虫は、ガの幼虫で、土の中に潜んでいて、作物の株もとと切ってしまいます。切られた株の近くの土の中に犯人が潜んでいることが多く、既に何匹かの犯人を捜して処刑することができました。
一方、アスパラガスは、昨年定植して今年2年目です。昨年は冷夏長雨のため、病気が多発しましたが、今年はどうなるでしょうか??
岸浩文
有機栽培11年目のほ場です。昨年は雑草(コナギ)の大発生に加えてイネミズゾウムシの被害で、収量は過去最低を記録してしまいました。今年も昨年のような稲の生育で、少し心配。
景山伸幸
景山会長のほ場は有機栽培なんと11年目。
今年も雑草対策は菜種粕。そろそろコナギが生えてきました。
分けつがやや少ないので、稲の株を抜いてびっくり!!。根がほとんどありません。抜いた株を水の中でふってみると、なにやら白い虫は浮かんでくるではないですか、これはイネミズゾウムスの幼虫。これが根をかじっているので稲に元気がないのでしょうね。 しかし有機栽培では対処法なし、ただ、稲の発育速度がイネミズゾウムシの食害を上回るのを待つのみです。
杉山憲一
ことらのほ場も有機栽培なんと11年目。研究熱心な杉山氏は、今年も、菜種粕やら液体マルチやら、いろんな方法で雑草対策に取り組んでます。